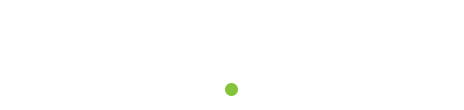研究科長挨拶

文学研究科長
小川 和也
文学研究科日本文学・日本語文化専攻、歴史文化専攻は、ともに、人文社会科学研究科に移行しており、現在、募集をしておりません。日本文学・日本語文化専攻、歴史文化専攻は、それぞれ、人文社会科学研究科の日本語日本文学専攻、歴史文化専攻として再編成されています。 なお、各専攻HPのURLは以下のとおりです。 ご関心のある方は、こちらをご参照ください。
日本語日本文学専攻 https://www.chukyo-u.ac.jp/educate/hass/study/japanese_language_and_literature.html
歴史文化専攻
https://www.chukyo-u.ac.jp/educate/hass/study/history_and_culture.html