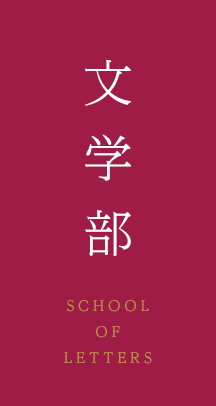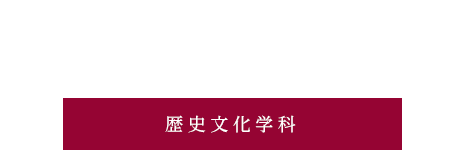-
准教授
小早川 道子(こばやかわ みちこ) -

自己紹介/プロフィール
愛知県出身。愛知県史編さん室勤務を経て、2014年度本学に着任。専門は日本民俗学。主に愛知県下の年中行事に関わる民俗について調査・研究活動をおこなっている。近年はハレの機会における魚食文化について研究を進めているほか、尾張東部や三重県北勢地域の「お月見どろぼう」などにも注目している。古老からの聞き取り等、フィールドワークをもとにした従来の民俗学的手法とあわせて、文献資料を使った民俗研究も模索している。
学会・公職活動
日本民俗学会、名古屋民俗研究会、名古屋郷土文化会、日本風俗史学会、まつり同好会、愛知県文化財保護審議会委員、三重県文化財保護審議会委員、日進市文化財保護審議会委員、大府市文化財保護審議会委員、半田市文化財専門委員、桑名市文化財保護審議会委員、豊橋市二川宿本陣資料館専門委員会委員、豊橋市美術博物館協議会委員、岡崎市美術博物館博物資料収集委員会委員、大府市史編さん委員会委員、津島市氷室作太夫家住居保存活用計画策定協議会委員
主な著書・論文
「三遠地域の信仰と宗教者―守札の習俗と津島御師の史料から―」『まつり』85、まつり同好会、2024年
「瀬戸内海周辺地域におけるハレの魚 ―岡山県の事例を中心に―」『佛教大学大学院紀要 文学研究科篇』52、佛教大学大学院、2024年
「伊勢湾周辺地域におけるボラの民俗―愛知県三河地域の事例を中心に―」『日本民俗学』316、日本民俗学会、2023年
「婚姻・産育儀礼における祝い魚―東浦町前日高家文書を中心に―」『中京大学文学会論叢』第7号、中京大学文学会、2021年
『新編知立市史7 資料編 民俗』(共著)知立市、2019年
『新修豊田市史17 別編 民俗Ⅲ 民俗の諸相』(共著)豊田市、2017
「「お月見どろぼう」の現状と研究視点」『中京大学文学部紀要』第51巻第1号、中京大学文学部、2016
『日進市史 民俗編』(共著)日進市、2015年
『新修豊田市史16 別編 民俗2 平地のくらし」(共著)豊田市、2015
「西三河平野部の『祭り魚』―ボラの地位と利用の変化について」『中京大学文学会論叢』第1号、中京大学文学会、2015
『新修豊田市史15 別編 民俗1 山地のくらし」(共著)豊田市、2013
『愛知県史 別編 民俗1 総論』(共著)愛知県、2011
『愛知県史 別編 民俗2 尾張』(共著)愛知県、2008
「尾張北部・東部の年中行事と農事暦」『愛知県史民俗調査報告書5 犬山・尾張東部』愛知県、2002
「津島御師の廻檀活動」 『愛知県史民俗調査報告書4 津島・尾張東部』愛知県、2001
ゼミ紹介

-
小早川 道子ゼミ
小早川ゼミでは、フィールドワークを中心とした民俗研究を行っています。フィールドワークを実施するには、まずテーマに関する予備知識が不可欠です。そのため、フィールドワークに臨む前に、文献などを使って、テーマについて徹底的に調べ上げます。フィールドワークと文献調査の併用が、小早川ゼミの特徴です。近年は尾張地域・三重県北勢地域の「お月見どろぼう」調査を実施し、報告集をまとめています。また、日進市旧市川家住宅の「お月見どろぼう」イベントにも協力し、子どもの遊びワークショップを実施しています。フィールドワークを通して、民俗調査の方法や、民俗の継承・活用などについて考える力を身につけることを目標にしています。

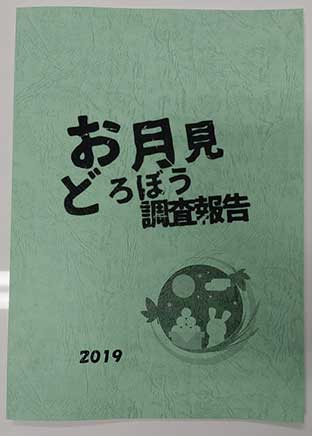
主な卒業研究タイトル
●川を渡る道―牛川の渡しを中心に―
●もうひとつの「知多四国」―四國直伝弘法大師尾張八十八ヶ所霊場―
●三月節供習俗の現状と観光化―ガンドウチを中心に―
●国府宮はだか祭の現状と継承―参与観察を中心に―
●現代民俗としての「お月見どろぼう」―愛知県と三重県の事例比較から―
●観光客が支える民俗芸能―白鳥踊りの現状と継承―
●現代の自治会の様相―山梨県富士吉田市中宿連合自治会を事例に―