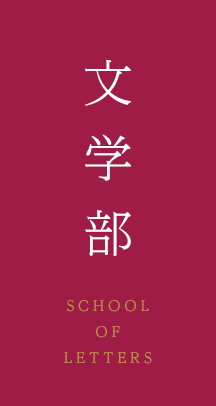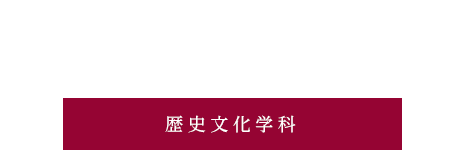-
准教授
小池 勝也(こいけ かつや) -

自己紹介/プロフィール
専門は日本中世史で、日本中世における政治と宗教の関係について研究している。特に、中世東国武家政権たる鎌倉幕府・鎌倉府と東国(関東)地域の寺社との関係に関心を寄せている。併せて、東国と畿内の宗教界の交流についても関心を持っており、その中間地域にあたる東海地域も含めて検討を深めていきたいと考えている。
学会・公職活動
史学会、歴史学研究会、日本歴史学会、日本古文書学会、中世史研究会、佛教史学会、千葉歴史学会、東アジア仏教研究会、栃木歴史文化研究会
主な著書・論文
「室町期鶴岡八幡宮における別当と供僧」(『史学雑誌』124編10号 史学会 2015年)
「南北朝末期の醍醐寺三宝院院主と理性院院主―宗助の座主就任の背景― 」(『日本歴史』813号 日本歴史学会 2016年)
「鎌倉末期から南北朝期にかけての聖尊法親王の動向―三宝院流定済方の分裂とその影響― 」(『鎌倉遺文研究』37号 鎌倉遺文研究会 2016年)
「南北朝・室町期における東国醍醐寺領と東国顕密仏教界の展開」 (『千葉史学』68号 千葉歴史学会 2016年)
室町期鶴岡八幡宮寺寺僧組織の基礎的考察(佐藤博信編『中世東国の社会と文化』 岩田書院、2016年)
「『輪王寺文書』における「上様」の語義について」(『歴史と文化』27号 栃木歴史文化研究会 2018年)
「中世東国寺社別当職をめぐる僧俗の都鄙関係―伊豆密厳院別当職問題を事例に―」(『歴史学研究』980号 歴史学研究会 2019年)
「中世における醍醐寺理性院流の展開と太元法」(『寺院史研究』16号 寺院史研究会 2020年)
「鶴岡八幡宮寺新宮の成立と展開」(『佛教史學研究』64巻1号 佛教史学会 2022年)
「室町期東国醍醐寺領と「中央の儀」」(『日本歴史』899号 日本歴史学会 2023年)
「室町幕府の知行保護法制と東国」(『年報中世史研究』49号 中世史研究会 2024年)
「中世東国武家政権と鎌倉顕密寺院」(『歴史学研究』1054号 歴史学研究会、2024年)
ゼミ紹介

-
小池 勝也ゼミ
小池ゼミは日本古代・中世史(主に室町期まで)の諸テーマで卒業論文を書くこと目指す人を対象としたゼミです。日本の古代・中世は、現代社会とは異質な部分が多くあり、その差異を探っていくのが醍醐味である一方で、現代日本文化の基層が築かれた時代であり、現代とのつながりという視点も重要であると考えます。3年次前期では、古代・中世史に関する学説史について論文を輪読する形で学習し、3年次後半から個々の学生の研究発表にうつり、3年次終了までに卒業論文テーマを明確にします。4年次は、卒業論文の執筆作業へと移り、その完成を目指してゼミの場で議論を行います。卒業論文の執筆は最終的には一人で行わねばならず、非常に孤独で厳しい戦いですが、ゼミのメンバーと叱咤激励しあいながら、この難題に取り組むことができる、厳しくも暖かみのあるゼミにしていければと思っています。
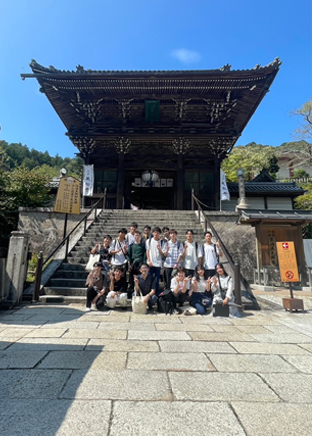
ゼミ旅行合宿 長谷寺門前にて
2024年度卒業研究タイトル
・古代関における軍事的性格の考察―律令三関を中心に城柵・古代山城等と比較する―
・唐との交流を通した奈良仏教の発展
・九世紀における斎王制度―賀茂斎院と伊勢斎宮の比較―
・古代女官の変遷過程―九世紀を中心に―
・平安宮廷における弓矢の呪術性―滝口の放つ弦音を中心に―
・平安時代における武士団の成立過程―東国における兵の登場と武士身分への昇華―
・東北地方における武士成立過程の研究
・古代から中世にかけての武具と兵法の変遷
・平清盛と権門寺院―対寺院関係からみた平家滅亡の要因
・鎌倉時代前中期における近衛流の摂関継承
・鳴海における鎌倉古道の変遷過程
・中世における諏訪氏大祝家と惣領家の成立過程
・『神皇正統記』執筆意図の考察―北畠親房の人物観―
・室町期における関氏と周辺勢力―長野氏・北畠氏を中心に―
・北畠満雅の乱後から室町時代後期にかけての北畠氏の動向―主に大和国での事例について―
・中世における遠江国府見付の自治都市的性格についての考察
・「門前町」宇治山田の形成